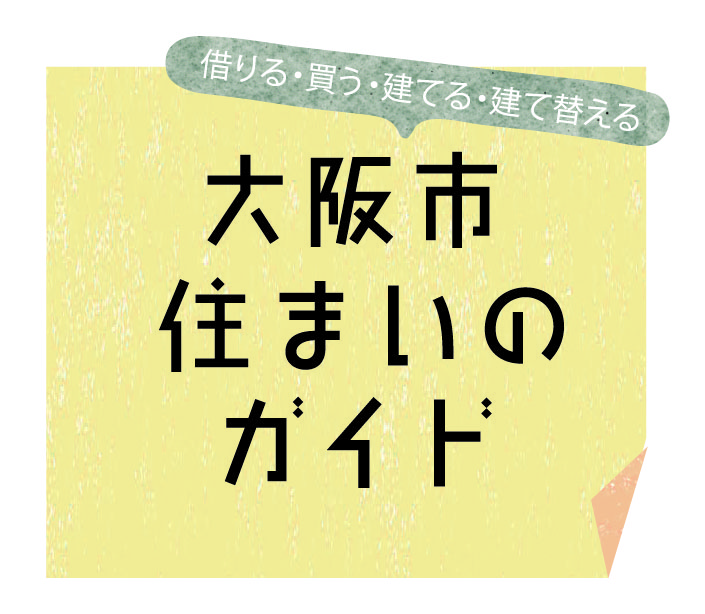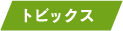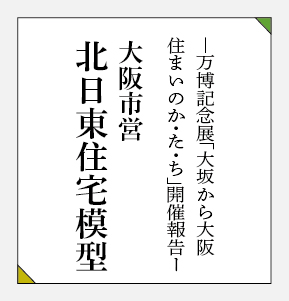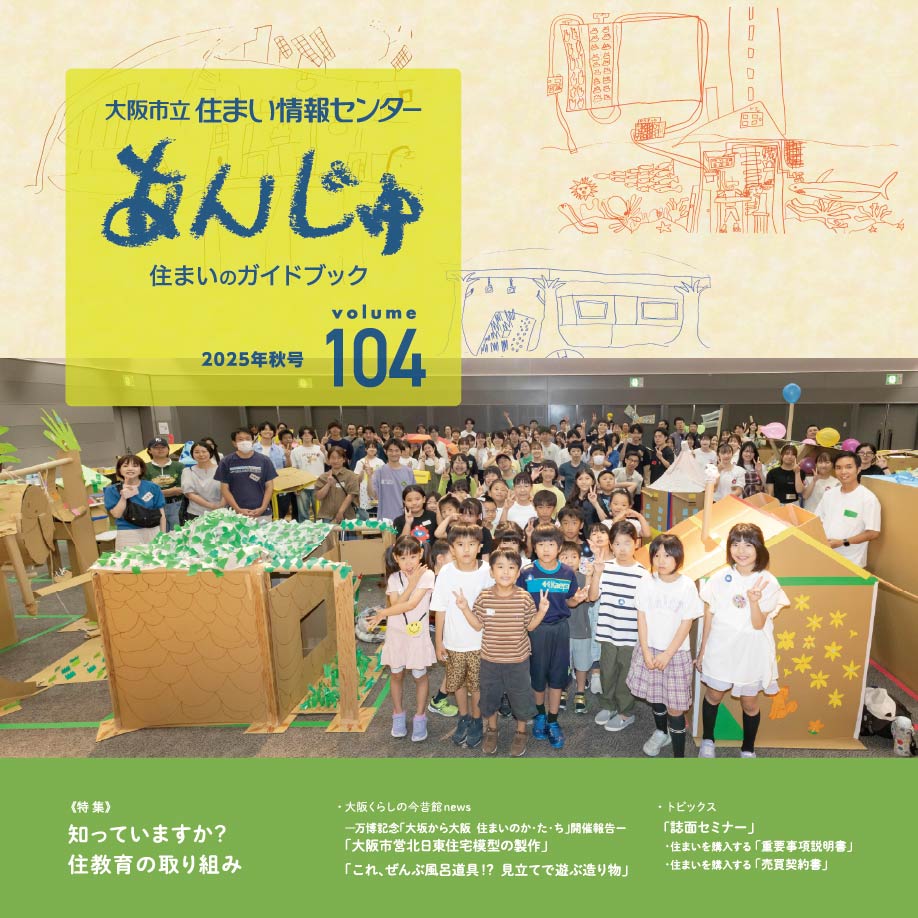 104
104
関川先生に聞く「住教育」ってなんですか?

関川 華さん
【PROFILE】
近畿大学建築学部建築学科准教授。フランスの集合住宅の管理体制について研究。近畿大学都市住宅研究室では住まいやまちづくりに関するあらゆるテーマを扱う。2022年より大阪市立住まい情報センター事業企画アドバイザー。
住教育とは
住教育とは、住宅に関するあらゆる意思決定をするために必要な知識を学習者が獲得することを意味します。ここでは、住教育のこれまでを振り返りつつ、今求められる住教育の方向性を考えてみます。
オクタヴィア・ヒルという人を知っていますか?
まず、住教育の重要性を感じて実践した人の昔話から始めましょう。それは、産業革命が起こったイギリスで、労働者向け賃貸住宅を経営したオクタヴィア・ヒルの話です。当時のロンドンでは、近郊農村から多くの労働者が集まりました。住宅が不足し、過密居住や路上生活をする者も珍しくありませんでした。それに対し、労働者の生活水準を改善しようとする社会活動家らが現れました。ヒルはその一人です。
ヒルは賃借人に、生活を改善する住宅管理の方法を積極的に伝えます。賃借人らが自主的な住宅管理をするようになり、共用空間の管理費用は随分と節約されました。その結果、節約された管理費で共用の庭が購入され、彼らの居住水準は飛躍的に向上しました。ヒルの活動は、オープンスペース運動と言われ、ナショナルトラストという有名な財団の設立に至りました。
住教育の目標とは何でしょう?
日本においても近代以降、労働者の住生活の改善について議論され始めます。現代になってからは教育の対象が子どもや国民全員へと広がります。例えば、昭和22(1947)年度の学習指導要領には「住居の科学的、能率的な使い方の会得」や「科学的、経済的な住宅・家具・造作の利用の能力」という目標が挙げられています。ヒルの例も踏まえると、住教育の目標とは、住み手自身が住環境に関わり、居住水準を改善する力を身につけることと捉えられます。
しかし、日本で住教育という考え方が出現してから今に至るまで、住教育には指導や学習の困難性があると言われ続けてきています。その理由は①内容が専門的で広範囲であること、②学習者の生活経験や階層性が多様であること、③住宅は地域性に強く影響されるので内容を一元的には捉えられないこと、などです。つまり、全ての人が異なる価値観や経験を持っているために、意思決定をするために必要な知識は「それぞれの人によって異なる」ということになってしまいます。では、無数の、そして多様な教育コンテンツがあれば、それぞれの人の住宅に対する意思決定が住環境の改善につながるのでしょうか?
その答えは、「昔はそうだったが、現在は変わりつつある」と言うのが適切でしょう。
これからの住教育とは?
現時点での住宅事情は個人レベルでは解決できない問題に迫られています。その一つが環境問題です。住宅は自然環境や地域に与える影響が他の物財よりも超絶に大きいという特徴を持っています。住宅を造っては壊す、スクラップアンドビルドは環境負荷を増大させます。さらに、住宅が周辺地域へ与える影響も絶大です。所有者不在の管理不全の空き家の増加は、災害発生時に思わぬ二次災害を引き起こすことがあります。
しかし、住宅の建設や所有、そして管理はあくまで個人の意思決定に委ねられています。個人の資産となる住宅に対するちょっとした意思決定が、インパクトが大きい環境負荷につながっていくことになるのです。
だからこそ、個々の人の好むと好まざるによらず、今以上に思慮深く、未来に対する配慮が求められています。「個々の居住水準を改善する知識」だけでなく、「持続可能な社会の一員として求められる住宅の知識」に目をむけるべき時期になっているのです。