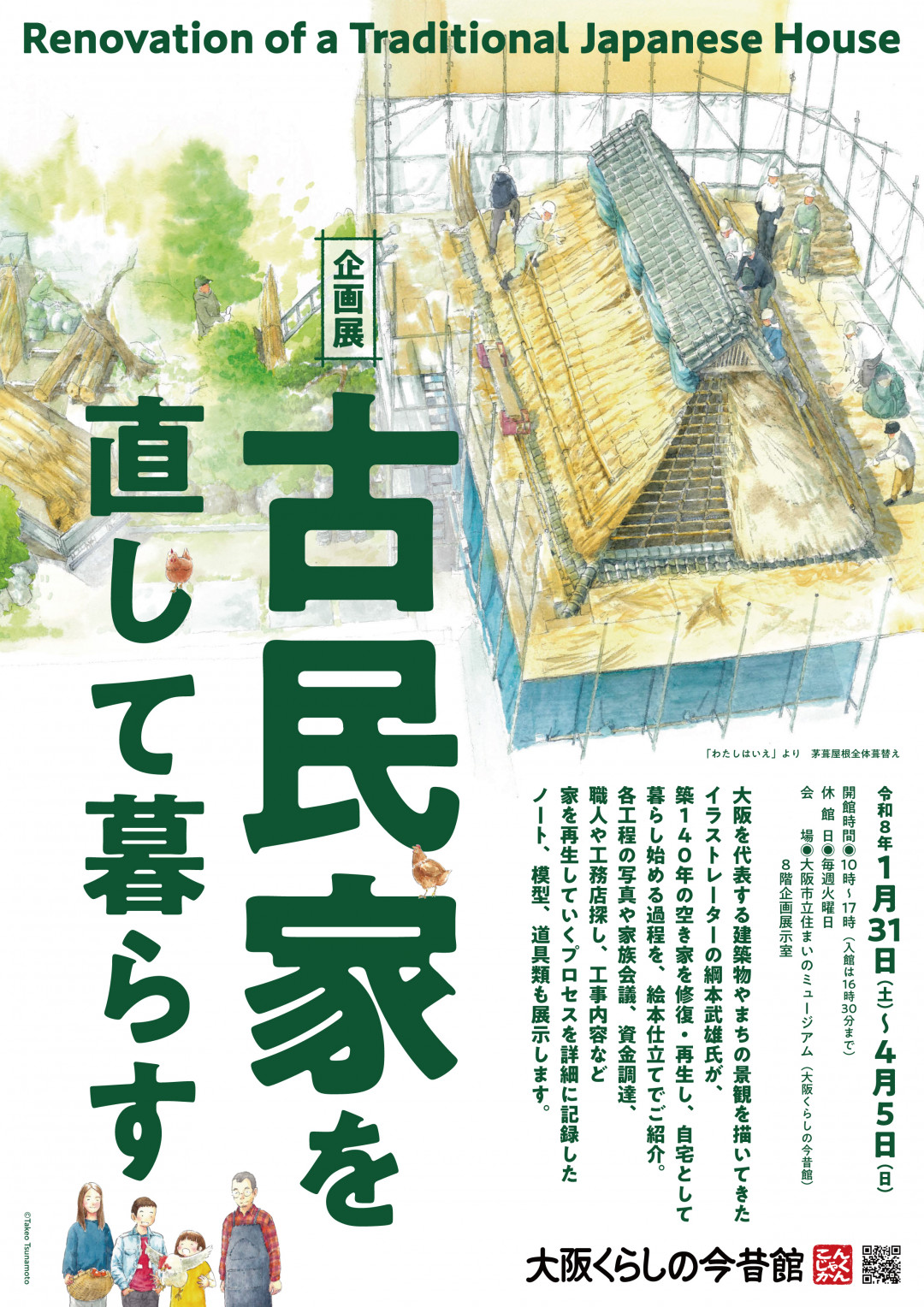江戸時代は天保のころ。大阪の町並みを実物大に復元しました。
表通りにはにぎやかな商家が建ち並び、裏通りには、長屋ぐらしの風景が楽しめます。
音声ガイド有料/¥100
人間国宝の落語家 桂米朝さんのガイドで展示を楽しんでいただけます。
4ヶ国語(日本語・英語・韓国語・中国語<繁体・簡体>)対応
桂米朝さんのガイドは日本語のみ
明治・大正・昭和・平成の大阪の住まいとくらしを、住まいの大阪六景を中心に精巧なからくり模型や映像で紹介します。
住まい劇場「あの日 あの家
ーある家族の住み替え物語ー」(約20分)
ーある家族の住み替え物語ー」(約20分)